あなたが写っているのを見て、なつかしくてメールしました。活躍しているのね。』
友人たちも、君に会いたがっていたよ。』
え?え?え?
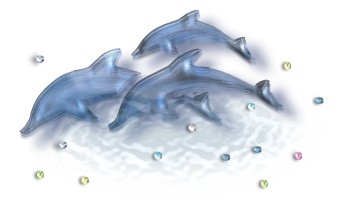
<From Sydney with love>
「悪い、どうしても抜けられない事情があるんだ。頼むよ。」
「それはよろしいですが。」
「すまん。」
泉田は阿部を片手で拝み、あわただしくドアから出て行った。
「どうしたの?」
その様子を自室のドアから出たところで見ていた涼子は、阿部の隣に行って尋ねた。
「いえ、今日の庁内の親睦飲み会の幹事を代わってほしいと。何かご都合があるようです。」
「ふぅん。珍しいわね、そういうくだらない行事の幹事は、いつも律儀に引き受けているのに。」
以前、どうしても行きたかったコンサートをその飲み会の為に断られたことがある涼子は、
見事な形の片眉をきゅっと上げた。
三連休明けの火曜日、何かと仕事は溜まっている。
泉田は組織犯罪対策部から、警務部と総務部の道場使用申込受付窓口に回り(涼子が参事官室の面々を鍛えなおすそうだ!)、
最後に警備部にたどりついた。
旧知の声が泉田を迎える。
「泉田センパイ、どうしたんですか?こんなところで。」
「来週の打ち合わせの資料を届けに来たんだ。相変わらず暇そうだな。」
「暇ではありません。僕は日本の治安を守るために昼夜を分かたず働いています。」
岸本は思い切り胸を張る。
・・・怪しいプライベートタイムにも存分に時間を使っているくせに。
そう突っ込みたかったが、そこから話が長くなってはかなわない。
「そりゃ熱心な御奉公、なによりだ。じゃあな。」
「あ、待ってくださいよ、泉田サン。今日の庁内の親睦飲み会、行くでしょ?」
「悪い、どうしても用があってな。あ、ここはお前さんが幹事だったか?あとは阿部に頼んであるから。」
「え〜、珍しいなあ、怪しいなあ。」
岸本は泉田の周りを好奇心満載の瞳で、ぐるぐると回る。
蹴飛ばしてやろうかと思わないでもないが、あることないこと涼子に告げ口されるのも片腹痛い。
「よんどころない事情なんだ、よろしく頼む。みんなからは評判いいぞ、キャリアで来てくれるのは優しい岸本さんだけだってな。」
「将来の布石として人望は欠かせません。」
さらにそっくりかえって胸を張る岸本は今にも後ろに倒れそうだが、泉田に支えてやる気は毛頭ない。
まあ、ノンキャリアの多い飲み会で、女性に警戒心を全く起こさせず、男性に反感を(さほど)買わずに、
参加出来る奇特なキャリア人材であることは事実だ。せいぜいがんばってもらおう。
「じゃあな。仕事しろよ。」
「だからしてますってば。」
泉田は岸本と警備部を後に、長い廊下を歩き始めた。
さて、いよいよ刑事部に戻るわけだが、今夜のことを涼子に言うべきか、言わざるべきか。
敏い彼女のことだ。必ずどこかで気づくだろう。
その時に、事実がまっすぐ伝わっていればいいが、どんな曲解をして耳に入っているかを考えるだに恐ろしい。
それに直属の部下に隠し事をされるというのは、決して気持ちのいいものではない、それは泉田にも分かる。
言おう。
泉田はそう決めると、話し出す順序を考えながらいつもより速度を落として参事官室への帰路についた。
「あ、そう。で?」
懸命の報告に、涼子は泉田が呆気にとられるほどシンプルな反応を返した。
「いえ、ご報告までにと思いましたので以上です。今日の飲み会の幹事については、阿部巡査に代わってもらいましたので、
庁内行事として刑事部に迷惑がかかることはありません。」
「それなら結構よ。今日はもう帰ってよし。」
「・・・ありがとうございます。失礼いたします。」
バタン。
閉じられたドアをきっとにらみつけると、涼子はドスンと参事官椅子に腰かけた。
ほどよいクッションが脱力した体を心地よく包み込んでくれる。
なんだって?元カノが帰ってきているから、今夜空港で会う?
それはいったいどういうこと?
そんなこといつ決めたの?!しかも会ってどうするの!!
「あの男は・・・ほんとに…。」
またきっと『会いたい』とか、『もう一度ちゃんとさよならがしたい』とか、そんなメールにふらついたに決まっている。
会ったら会ったで…。
「どうするだろう。」
意外ときっぱり区切りをつけそうな気がする。たとえ彼女が復縁を口にしても、
今更元に戻るのは不誠実だとか不道徳だとか、そんな固いことを繰り返しながら。
「でも・・・。」
やっぱり、相手の涙には勝てない。
たぶん、そういう男。
涼子に言わせれば、なぜ別れたのかわからない2人だ。
いったい相手の女性は泉田に何の不満があるのか。
優柔不断だとか野暮だとか鈍感だとかワーカーホリックだとか、そんな欠点は結構日頃からあからさまだ。
当然それを承知で付き合い始めたのだろう。
ならばなぜ?
そしてそれを乗り越えればまた2人は元に戻るのか?
「・・・バカバカしい。」
考え込んでいる自分に気づいて、涼子は天井を見上げ大きく伸びをすると、立ち上がった。
膝がかすかに震えている。
こんなにも怖いのだ、泉田を失うことが。
自分の素直な反応に、涼子はふっと笑ってわざと元気よく鞄を肩にかけた。
ここで見えない影におびえていても仕方ない。
「お先に。」
部下たちに声をかけ、部屋を出る。
そう、こんな日はとびきり上等のエステで自分を磨くか、前から思っていたスーツをあつらえにいくか、
それとも銀座で買い物三昧か。
間違っても一人で立ち止まっちゃいけない。きっとまた余計なことを考える。
そんなことを考えながら1階まで降りると、思わぬ人物に出くわした。
「おユキ…。」
「あら、お涼。」
涼子は、帰り支度の由紀子の腕をがしっとつかんだ。
「何?」
「あんたでいいわ、つきあいなさい。夕食に行くわよ。」
「なんでわたしが?」
「いいから、同期同士の旧交を温め合おうって言ってんのよ、それとも逃げるの?」
由紀子はしばし涼子の目を不信の念をこめて見つめたが、やがて首をかしげ頷いた。
「結構よ、どういう風の吹きまわしか知らないけれど、お付き合いいたしましょう。ただし行くなら…。」
「当然一流どころよ。」
「・・・お手並み拝見いたしましょう。」
警視庁二大才女の同行退庁にロビーがざわめく。
その中を、涼子と由紀子は颯爽と夜の街へ踏み出していった。

別れは電話一本だった。
『来週シドニーに発つの。向こうの出版社で働くことにしたから。さよなら。』
海の向こうに行くのが、彼女にとって夢だったから、それが叶うなら手を放していいと思った。
「行くな」と言えば止めてくれるなんて、そんなうぬぼれも身勝手も自信もなかった。
ただ後悔していたのは、彼女を傷つけたであろうこと。
今回の彼女からのメールは、いわばその赦しだ。
ならばせめて一度は応えねばなるまい。そう思った。
到着間際の成田エクスプレスの窓に映る自分の顔、こんな顔を見るのは久しぶりだと泉田は思った。
思い惑う男の顔・・・か。上司に『情けない!』と一喝されそうな。
電車がホームに滑り込む。
階段を駆け上がり、小走りで待ち合わせの場所に向かう。
ざわめくフロアの中に、記憶の中より少しスレンダーになり、髪が長くなった彼女が立っている。
彼女はこちらを見とめてにっこりと微笑んだ。
「久しぶり。忙しいのにごめんね。」
「いや、メールをありがとう。帰り間際に遅くなってすまない。」
「チェックインは終わっているけど、あと30分くらいしかないの。お茶しない?」
「ああ。」
心地の良い会話とリズム。
ただ小柄な彼女に合わせる目線の位置の新鮮さに、会わない時間が長かったことに気づく。
彼女の手荷物を持ち、すぐそばのカフェに入り、カウンターで飲み物をオーダーする。
「払っておくから席を取っていてくれないか?」
「わかった。」
彼女が泉田の為にカウンターの灰皿を掴んで、ひょいひょいと人の間を縫って席を探す。
あの頃と変わらない仕草、それはとても自然で愛おしくて。
その小さな背中を見ながら、痛む胸を抱えて、
泉田は初めて、大切な恋を失くしたことを文字通り痛感した。
「そう、泉田警部補が。…お行儀が悪いわよ、お涼。」
「ほおっておいてよ。それよりこのワインさすがね。」
都内某フランス料理店。
一族馴染みの上顧客2人の突然の来店に、支配人からメインシェフまで、店内中が色めき立った。
奥の個室に通り、当然のごとくに最上級のシェフのお勧めをそろってオーダーし、
2人は、非の打ちどころのない態度で
『用事があれば呼び鈴を鳴らします、入る時にも呼び鈴を鳴らしてね』と人払いの念を押してから、食事を始めた。
・・・で、涼子がコトここに至った理由を由紀子に説明して、
テーブルに肘をつきながら、ヴィンテージワインのがぶ飲みを始めたところだ。
「別れた男になんて、あたしなら二度と会わないわ。」
グラスを傾けながら、涼子は言った。
「不本意ながら同感よ。でも、泉田警部補の方はもしかしたら・・・。」
「もしかしたら、何?」
「謝りたかったのかもしれないわね。」
鴨を丁寧に切り分けながら、由紀子はつぶやいた。
「謝る?振られたって聞いてるけど?」
「そこまで追い詰めるほど傷つけたって思っているのかもしれないでしょう?」
ふんと涼子はそっぽをむいて、グラスを煽った。
「ばかばかしい。振られた相手をいたわる必要がどこにあるの?負けてなお相手に情けをかけるなんて愚の骨頂ね。」
「私もそう思うけれど・・・でも。」
由紀子は空になった涼子のグラスにワインをついでもらうべく、ソムリエを呼びながら微笑んだ。
「恋愛の結末や望む幸せの形を、『誰かと比べる』ことは無意味なのよ。
だからきっと泉田警部補は、彼なりの恋愛の結末をつけたかったんじゃないかと思って。」
涼子はその言葉に眼をぱちくりとさせると、由紀子をじっと見つめた。
「な、何よ?」
「いや…久しぶりに少女マンガの脇役みたいな台詞を聞いたなと思って。」
「…その脇役って言うのはどういうことかしら?」
「主人公が落ち込むと何か説教めいたことを言って、話を進める脇役がいるじゃない?あんな感じ。」
由紀子は上がりかけた眉を、戸惑ったようにしかめた。
怒っていいのかどうかよくわからない。あながちけなされているのでもないらしい。
何より、今日の涼子は妙に素直だ。
「渡したくないんだよね…。」
涼子がつぶやく。
そう、それが本音。
由紀子は苦笑いでワインリストを広げた。
「…同感よ。次は何にする?私も今日は思い切り頂こうかな。」
「そう…すごいね、海外生活にもすっかり慣れているみたいだ。」
「そうね。まだやっぱりなかなか仕事は取れないけれど。」
たあいない近況報告が終わると、切り込んできたのは彼女の方だった。
「結婚するの?この上司と。」
ぶっ。
泉田はすんでのところでコーヒーを吹き出すのをこらえた。
彼女の指さす先には、広げられた手帳型のスクラップブックとそこに貼られたザナドゥランドでの記事写真。
小さく涼子と泉田が写っている。
「いや!…まだそんな予定はない。」
否定は大きく、しかし説明が難しいので後半はやや小さめに。
そんな泉田を見て、彼女はころころと笑った。
「あいかわらずねえ。みんな言ってたわよ。泉田はもう尻に敷かれているんだから、いっそ観念すればいいって。」
「…あいつらとちゃんと連絡を取っているんだな。」
泉田と彼女の間にいる、多くの共通の友人たち。
泉田は、自分のせいで彼女が彼らと気まずくなっていないだろうかとずっと心配していた。
しかし杞憂だったようだ。
「そうね、みんな元気そうよ。あなたから連絡がないのを逆に心配していたわ。
海を超えてそんなことを私に言われても困るんだけどね。」
そうだ、いつも忙しい泉田に代わって彼女が彼らとの間をつないでいてくれていた。
彼女がいなくなってから御無沙汰しているのはむしろ泉田の方ということか。
「君は?同居している彼とは?」
「あ、なんとなく刑事さんの尋問口調ね。」
さりげなく聞いたつもりが、やはり口調は固かったようだ。
「すまない。」
「いいの。聞いてくれてありがとう。うまくいっているわ。大切にしてもらっている。」
彼女は微笑んだ。
その微笑みは、昔何か嬉しいことや楽しいことがあった時に見せていたものと同じで、泉田はほっと息をついた。
そして何より言わねばならないことを、やっと口に出した。
「何よりだ。君にずっと謝りたかった…つらい思いをさせたと思う。ごめん。」
「あれ?謝るのは私の方よ。」
え?
泉田は彼女の目を見た。彼女はいたずらっぽく笑って泉田の額をつついた。
「心配させたかったの。ダイエットでもすれば心配してくれるんじゃないか、私の方を見てくれるんじゃないかって。
気を使ったでしょう?ごめんね。」
「いや、それは…。」
「でも私も、そんな自分がいやになったの。あなたを疲れさせて、自分を苦しめて、そんな人生最低よね。
…いつまでもそばにいられるわけもなかったのよ。あなたは刑事の仕事が大好きで、私は私らしく夢を持っていて。
で、そんなお互いが好きだったんだから、奇跡でも起きない限りどこかで終わりにしなきゃしょうがないわよね。」
「・・・。」
泉田は思わず長い間口に出さなかった、彼女のファーストネームをつぶやいた。
彼女は一瞬瞳を揺らして、そしてにっこりと笑った。
「来てくれてありがとう。私の人生にたくさんの幸せをくれてありがとう。
大丈夫、きっと私もあなたも、何もかもうまくいくわ。」
彼女が差し出した手を泉田は握り返した。
そして立ち上がる彼女について、店を出る。
「ここでいいわ、じゃあ元気で。」
泉田は彼女の手荷物を返すとゆっくりと告げた。
「…本当は真っ先に言うべきだったんだけれど…君はとてもきれいになった。幸せになってくれ。」
彼女は呆気にとられて泉田を見つめ、そしてまたころころと笑って手を振った。
「…今の上司も苦労しているんでしょうねえ、そういうところ。気をつけた方がいいわよ。」
「え?」
「変わっていなくて安心した、じゃあね、またメールちょうだい。」
「ああ、気をつけて。」
彼女は、泉田に背を向けて歩き出した。
視界が潤む。涙が頬をつたう。
まっすぐな人、いつも大切なことが何かをちゃんとわかってくれている人、どこまでも守ってくれると信頼できる人。
だからふいに贈られる真摯な言葉に、心ごと包み込まれ持っていかれそうになる。
――幸せに。
出国ロビーに続く長いエスカレーターで、彼女は最後にそうつぶやいた。

2時間後。
成田エクスプレスを降りた泉田は、感傷に浸る暇もなく、タクシーで涼子とよく行くバーへ急いだ。
ドアを開けると、カウンターにうつ伏せている涼子の髪をもてあそぶ由紀子の姿が目に飛び込んでくる。
「あ、あの、室町警視、これは…。」
「ああ、呼び出してごめんなさい。お涼が酔い潰れちゃって。送ってあげてもらえるかしら。」
「それはもちろんですが・・・。」
彼女と空港で別れてすぐ、携帯の呼び出し音に我に返ると、厳しい由紀子の声が浴びせられた。
――泉田警部補、職務を忘れているのではないの?すぐに戻りなさい。場所は…。
「あの・・・。」
「ごめんなさい、あの呼び出しは職権乱用ね。謝るわ。」
「いえ、それはいいのですが…。」
由紀子はくすくすと笑いながら、立ち上がった。体がゆらりと揺れる。こちらも相当飲んでいるらしい。
「あの、室町警視、表に乗ってきたタクシーを待たせています。先にそちらを使って下さい。
それとも先にお送りした方が…。」
心配そうな泉田の声に、由紀子は微笑んで手を振った。
「来てくれてよかった。ありがとう、タクシーは使わせて頂くわ。泉田警部補も気をつけて。」
涼子の頭をぽんぽんと叩くと、由紀子は泉田に軽く一礼してドアを出て行った。
泉田も一礼してその後姿を見送ると、涼子の隣に行き、その体を抱えあげて立たせた。
「警視、帰りますよ。しっかりと立ってください。歩けますか?」
一瞬涼子がぱちぱちと目をしばたかせるが、またくったりとすぐ目を閉じる。
まったく、他愛のない。はた迷惑な。
泉田はくすりと笑った。
さっきまでの出来事が嘘のようだ。そう、これが泉田の今、そして現実。
支払が終わっていることをバーテンダーに確認すると、泉田は涼子を支えて店を後にしたのだった。

「ふ〜ん、オフィシャルアドレス宛てに私信返信とはいい度胸ね。」
「け、警視っ!」
早朝の参事官室。泉田のPCを、後ろから涼子が覗き込んでいる。
「いえ、これはその、おかしいな…。」
泉田は返事に窮した。
この警視庁で持っているアドレスの方に返信が来るとは、彼自身が一番予想していなかった。
その前のメールまでは、ちゃんと自宅のPC宛になっていたのに。
それは彼女のささやかな復讐、泉田は気がつかなくても涼子はちゃんと気づいている。
「マリアナ海溝を超えてまで、これ以上あたしの秘書にちょっかい出すなら、
フィリピン上空あたりの乱気流で叩き落としてくれるわ!ふっふっふっ。」
そうつぶやくと、涼子は出勤してきた丸岡の挨拶に軽く手を振り、狼狽している泉田をおいて、
自身の執務室に引き上げた。
今朝、目覚めたら自分のベッドに寝ていた。
泉田が運んできてくれたのだと、マリとリューが教えてくれた。
支えてくれていた腕のぬくもりのかすかな記憶が、
それ以上何も聞かなくても、
朝の光とともに、今彼の一番に近くにいるのは自分だという自信を持たせてくれる。
…ただし、後に残ったやっかいごとがひとつ。
涼子は昨日と同じクラッチバックから、中に入っていた一枚のメモを取り出した。
達筆の数字、内容は昨夜の精算金額。
成り行き上、共同戦線をはってしまったもう一人の恋敵の字だ。
とにかくこの借りを早く返しに行かねばならない。
涼子は立ち上がり部屋を出た。
「泉田クン、時代遅れの少女マンガの脇役のところに行くわよ。お供しなさい。」
「は?はい。」
泉田が立ち上がる。
いい顔をしている、と涼子は思った。何かが吹っ切れた顔だ。
よし、この顔を見せることで、一晩分の利子は踏み倒してやる。
2人の姿が廊下に消え、やがて画面に表示されたメールを、スクリーンセーバーが覆い隠していった。
代わって大きく表示された文字は、『勝てば官軍』。
(END)
*週末たくさんのご訪問を頂戴していたのに、遅くなって申し訳ありません。
モトカノの性格や背格好は捏造につき、本作で出てきて相違したらもちろん潔く下げます。ご了承ください。
でも今でもほんの少しは泉田クンのことが好きならいいな。